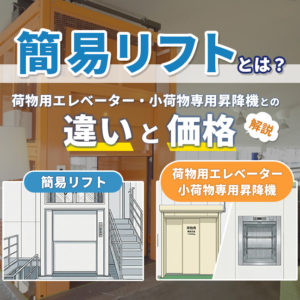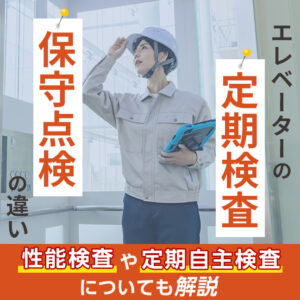豆知識
エレベーター事故の事例・原因・確率|安全対策を専門家が解説
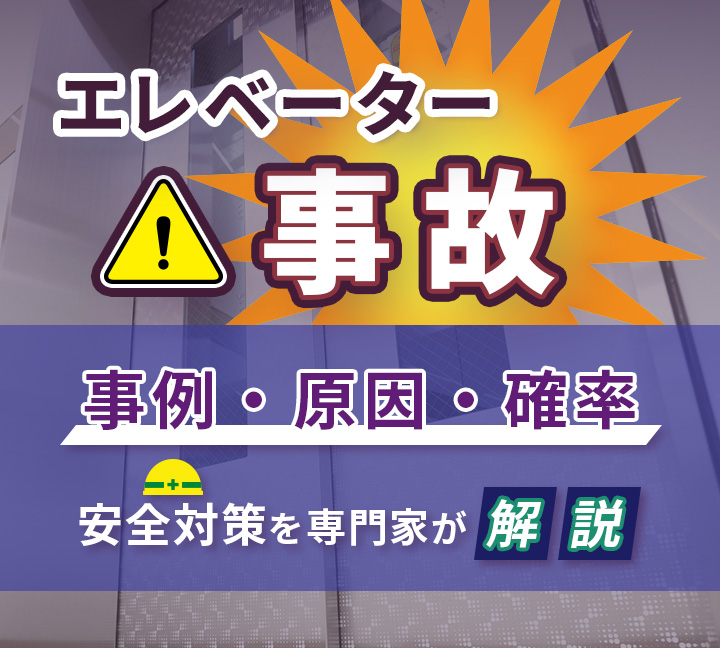
「ニュースでエレベーター事故の報道を見たけれど、うちのマンションは大丈夫だろうか…」
「最近、ドアの閉まるタイミングがおかしい気がする。万が一、重大な事故に繋がったら…」
マンションの管理組合理事やビルのオーナーという責任ある立場として、施設の安全、特にエレベーターの安全性に対する不安は尽きないものですよね。
居住者や利用者の命を預かる設備だからこそ、そのリスクには人一倍敏感になるのは当然のことです。
しかし、漠然とした不安を抱えているだけでは、具体的な対策は打てません。
管理者として本当に必要なのは、事故の原因を正しく理解し、法的責任の範囲を知り、そして具体的な予防策を講じることです。
この記事では、実際にどのような事故がなぜ起きるのかという具体的な原因、管理者として知っておくべき法的な責任、そして事故を未然に防ぐために今すぐ何をすべきかという明確な対策まで、専門家が徹底的に解説します。
目次
エレベーター事故の発生状況と3大原因
まず、エレベーター事故がどれくらいの確率で、どのような原因で起きているのか、客観的なデータから見ていきましょう。
過度に恐れる必要はありませんが、リスクを正しく認識することが、適切な対策の第一歩です。
国内における事故の発生確率と統計データ
エレベーターにおける死亡・重傷事故の報告件数は、全国で年間数件程度で推移しています。
日本のエレベーター設置台数が約110万台であることを考えると、重大事故の発生確率は極めて低いと言えます。
これは、日本のエレベーターが非常に高い安全基準で作られ、維持管理されていることの証です。
しかし、一方で閉じ込めや軽微な挟まれといった不具合は、より多く発生しており、事故がゼロではないという現実も直視しなければなりません。
事故原因のほとんどは経年劣化・保守不備・旧式装置
では、なぜ稀に事故が起きてしまうのでしょうか。その原因は、大きく分けて以下の3つに集約されます。
- 部品の経年劣化
エレベーターは数万点の部品からなる精密機械です。長年の使用により、ワイヤーロープやブレーキ、制御部品などが摩耗・劣化し、本来の性能を発揮できなくなることがあります。 - 不適切なメンテナンス(保守不備)
定期的なメンテナンスが適切に行われていないと、劣化のサインを見逃してしまいます。コスト削減のために安価すぎる業者に依頼した結果、必要な点検項目が省略されていた、というケースも少なくありません。 - 旧式の安全装置の性能限界
現在の安全基準では必須とされている装置(後述します)が、古いエレベーターには設置されていないケースがあり、それが事故の一因となることがあります。
重要なのは、これらの原因の多くは、適切な維持管理と計画的な改修によって、未然に防ぐことが可能であるという点です。
過去の事故事例から学ぶ事故の種類と危険性
次に、実際にどのような事故が起きているのか、具体的な事例を見ていきましょう。
過去の事例から学ぶことで、あなたの施設に潜むリスクをより具体的にイメージすることができます。
最も多い戸(ドア)挟まれ事故とドアセンサーの限界
エレベーター事故の中で、発生件数が最も多いのが、ドアに人や物が挟まれる事故です。
特に、旧式のドアセンサー(セーフティシュー)などは、ドアの端の接触部分に物が当たらないと作動しません。
そのため、ペットのリード、台車のひもなど細い物がセンサーに検知されずに挟まれてしまう事故が後を絶ちません。
最新の「マルチビームドアセンサー」であれば防げる事故であり、旧式センサーの性能限界が浮き彫りになっています。
人命に関わる戸開走行事故と安全装置の重要性
最も重大な事故の一つが、ドアが開いたまま、かごが昇降してしまう「戸開走行(こかいそうこう)事故」です。
利用者が乗り降りする瞬間に発生すれば、命に関わる極めて危険な事故につながります。
過去には、この事故で人命が失われるという痛ましい事例も発生しました。
この事故の主な原因は、ブレーキ系統や制御回路の故障です。
この種の事故を防ぐため、現在では「戸開走行保護装置(UCMP)」の設置が義務付けられていますが、古いエレベーターには未設置のものが多く存在します。
過去の重大事故を教訓に、法改正によって義務化された重要な安全装置です。
閉じ込め・床との段差による事故
ニュースでもよく耳にする「閉じ込め」も、頻度の高い事故の一つです。
機器の故障や停電が主な原因ですが、長時間にわたる閉鎖空間での待機は、特に高齢者や体調の悪い方にとっては大きな心身の負担となります。
また、エレベーターが目的の階に正確に停止せず、床との間に数センチの段差ができたことで、乗り降りの際につまずいて転倒し、怪我をするという事故も発生しています。
これらの事故も、適切な点検や計画的なリニューアルで防ぐことが可能です。
参考:建物事故予防ナレッジベース「エレベーター事故事例検索結果」
管理者(所有者)が負うべき法的責任と義務
「事故が起きたら、メンテナンス会社の責任だろう」そう考える方もいるかもしれません。
しかし、法律ではエレベーターの安全に関する第一次的な責任は、その管理者(所有者)にあると定められています。
定期検査報告の義務(建築基準法第12条)
エレベーターの所有者・管理者は、建築基準法第12条に基づき、年に一度、専門の資格者による検査を受け、その結果を特定行政庁(市役所など)に報告することが義務付けられています。
これを「定期検査報告」と言います。 この報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合は、法律により罰せられる可能性があります。
これは、エレベーターの安全を維持するための、所有者の最低限の義務です。
事故発生時に問われる損害賠償責任
もし事故によって利用者に損害を与えてしまった場合、所有者・管理者は、民法上の「工作物責任」に基づき、被害者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
「きちんと保守会社と契約していたから、責任はない」とは必ずしも言えません。
例えば、保守会社から部品交換や改修の提案を受けていたにもかかわらず、コストを理由にそれを放置し、結果として事故が起きた場合、管理者の責任が重く問われる可能性があります。
事故を未然に防ぐ管理者が今すぐやるべき2大対策
では、管理者として事故を未然に防ぎ、責任を果たすためには、具体的に何をすべきなのでしょうか。その答えは、「日々の安全」と「未来の安全」という2つの視点での対策に集約されます。
対策1:日々の安全を守る「信頼できる保守契約」
エレベーターの安全は、日々の適切な保守点検によって支えられています。
最も重要な対策は、信頼できる専門業者と、適切な内容の保守契約を結ぶことです。
単に価格が安いという理由だけで業者を選ぶのは非常に危険です。
以下の点を確認し、本当に信頼できるパートナーを選びましょう。
- 実績は十分か: 多くのエレベーターの保守を手掛けてきた実績があるか。
- 対応は迅速か: 故障や閉じ込め発生時に、すぐに駆けつけてくれる体制があるか。
- 報告は丁寧か: 点検内容や部品の状態について、専門用語ばかりでなく、素人にも分かりやすく説明してくれるか。
価格の安さだけで業者を選ぶことは、将来の大きなリスクを抱え込むことと同義です。
複数の業者から見積もりを取り、サービス内容と価格のバランスを慎重に見極め、信頼できるパートナーを選ぶことが何よりも重要です。
対策2:根本的な危険を断つ「安全装置の近代化改修」
日々のメンテナンスで部品の劣化を防ぐことはできても、20年前の安全基準で設計されたエレベーターの性能限界を覆すことはできません。
前述した「戸開走行保護装置」や、ドアの挟まれ事故を防ぐ「マルチビームドアセンサー」など、現在の安全基準で求められている安全装置を後付けで設置することは、事故のリスクを根本的に断つための最も確実な対策です。
古いエレベーターを丸ごと交換する「リニューアル」に比べて費用を抑えつつ、安全性だけを最新のレベルに引き上げることができます。
あなたの施設のエレベーターに、これらの装置が付いているか、一度確認してみてください。
エレベーター事故に関するよくある質問
最後に、エレベーターの事故や安全に関して、皆様からよく寄せられる質問にお答えします。
閉じ込められた場合の正しい対処法は
万が一、エレベーターに閉じ込められてしまった場合は、絶対にドアをこじ開けようとせず、落ち着いてかごの中にある「非常ボタン」を押してください。
外部の管理室や保守会社に繋がり、専門の技術者が救出に向かいます。
多くのエレベーターには停電時自動着床装置が付いているため、停電でも数分で復旧することがほとんどです。
現在の保守契約で十分か確認する方法は
まずは、現在の保守会社から毎月、あるいは四半期ごとに提出される「点検報告書」にしっかりと目を通しましょう。
そこに「要是正」「要交換」といった指摘事項が記載されていないかを確認します。
もし、報告書の内容が分かりにくい、あるいは対応に不安を感じる場合は、他の独立系保守会社に「無料診断」を依頼し、第三者の目で現在のエレベーターの状態と保守内容を評価してもらうことをお勧めします。
安全装置の後付けは可能か
はい、ほとんどのケースで可能です。
特に、ドアの安全性を飛躍的に向上させる「マルチビームドアセンサー」や、重大事故を防ぐ「戸開走行保護装置(UCMP)」は、多くのマンションやビルで後付け改修が行われています。
費用や工期はエレベーターの状況によって異なりますので、専門業者に見積もりを依頼しましょう。
まとめ
この記事では、エレベーターの事故について、その発生確率や原因、そして管理者として知るべき法的責任と具体的な対策について詳しく解説してきました。
お伝えしたかった最も重要なことは、エレベーターの安全は、「運」や「偶然」によって保たれているのではなく、「適切な維持管理」という日々の地道な積み重ねによってのみ、実現されるということです。
そして、その適切な維持管理を行う責任は、最終的に所有者・管理者であるあなたにある、という厳然たる事実です。
事故のリスクをゼロにすることはできません。
しかし、そのリスクを限りなくゼロに近づけることは可能です。
- 信頼できる保守パートナーを選ぶこと。
- 経年劣化に対して、計画的なリニューアルを検討すること。
- 最新の安全装置を導入し、積極的に安全性を向上させること。
これらが、管理者として、そして居住者や利用者の安全を守る責任者として、今すぐできる最善の行動です。
もし、あなたの施設のエレベーターの安全性に少しでも不安を感じたら、私たちアイニチ株式会社にぜひご相談ください。
専門家として、あなたの施設の現状を正確に診断し、最も効果的で費用対効果の高い安全対策をご提案することをお約束します。

関連記事
当社スタッフがお客様の昇降機(エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機)の状況(使用年数、故障箇所、不具合)等を伺い、必要であればリニューアル・部品交換も視野に入れた最善策をご提案いたします。
アイニチは、仙台・千葉・埼玉・東京・神奈川・名古屋・大阪・岡山・福岡の全国9箇所の拠点だけでなく、専門会社とパートナーシップを結び、全国すべての都道府県をカバーしています。(一部離島を除く)全国どこでも迅速な対応が可能です。
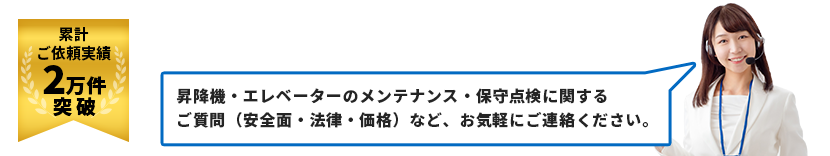

まずはお気軽にご連絡ください
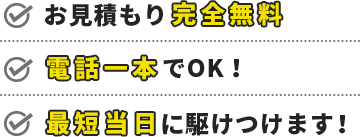
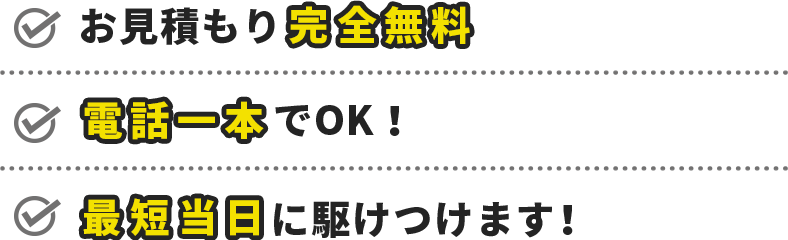
お電話でのお問い合わせ (営業時間8:30~17:30)