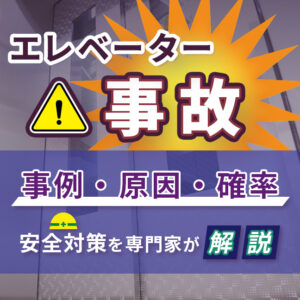豆知識
マンションのエレベーター交換費用は?時期・方法・業者選び
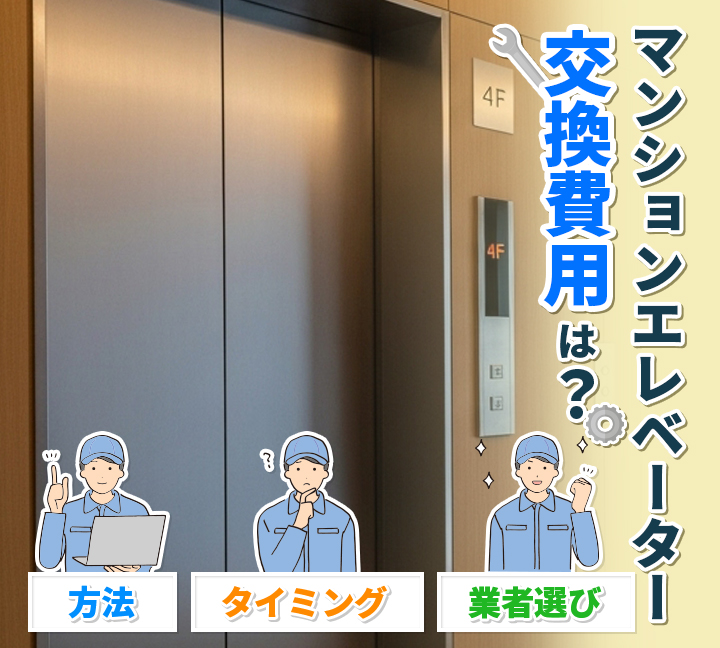
マンションに欠かせないエレベーター。毎日の暮らしや高齢者・小さなお子さまにとっては特に重要な設備ですが、実は寿命があり、一定の年数が経過すると「交換」を検討しなければなりません。
しかし、いざ交換の話が持ち上がると「どれくらいの費用がかかるのか?」「住民への影響は?」「どの業者に頼めば安心なのか?」といった不安や疑問が次々と出てきます。
特にマンションの管理組合にとっては、数百万円〜数千万円規模の大きな出費となるため、「まだ交換しなくてもいいのでは?」と判断を迷うケースも少なくありません。
ですが、故障が増えたり、メーカーから部品供給が止まったりすると、住民の安全や生活に直接支障をきたす恐れがあります。
「本当に今、交換が必要なのか?」
「どのくらいの予算を見込めばいいのか?」
「信頼できる業者をどう選べばいいのか?」
そんな疑問を抱える管理組合や居住者の方に向けて、本記事ではマンションのエレベーター交換について、寿命のサインから費用相場、工法の種類、進め方、そして業者選びのポイントまでをわかりやすく解説します。読んだ後には、交換の必要性と適切な進め方がイメージできるはずです。
目次
マンションのエレベーター交換を検討すべき寿命のサイン
エレベーターの交換は、多額の費用がかかるため、適切なタイミングを見極めることが非常に重要です。
まだ使えるのに交換してしまっては無駄な出費になりますし、逆にタイミングを逃すと、ある日突然エレベーターが止まってしまうリスクもあります。
ここでは、交換を検討すべき具体的な「3つのサイン」について解説します。
法定耐用年数と税法上の減価償却期間
エレベーターの寿命を考えるとき、よく耳にするのが「法定耐用年数」という言葉です。
税法上、エレベーターの減価償却資産としての法定耐用年数は「17年」と定められています。
これはあくまで税務上の資産価値を計算するための年数であり、「17年経ったら使えなくなる」という意味ではありません。
一方で、国土交通省が公開している「長期修繕計画作成ガイドライン」では、エレベーターの交換周期の目安は「20年~30年」とされています。
一般的には、設置から25年前後で、多くのマンションが大規模なリニューアル(交換)工事を計画・実施しています。
異音・振動・頻繁な故障
日々の運転の中に、交換を検討すべきサインが隠れていることがあります。
- 停止時の大きな揺れや「ガクン」という衝撃
- 走行中の不自然な振動や「ゴトゴト」という異音
- ドアの開閉がスムーズでなく、異音がする
- ボタンの反応が悪い、または点灯しない
- 「故障中」の貼り紙を見る回数が明らかに増えた
これらは、モーターや制御部品、ワイヤーロープといった主要なパーツが経年劣化しているサインです。小さな不具合でも、放置すれば大きな事故に繋がる危険性があります。
故障が頻繁に起こるようになったら、それは交換・リニューアルを本格的に検討すべき重要な警告と捉えましょう。
メーカーからの部品供給停止通知
これが、交換を検討せざるを得ない、最も決定的な通知です。
エレベーターの制御部品などの電子部品は、技術革新のスピードが速いため、製造メーカーは一定期間(通常は製造中止から約10年~20年)を過ぎると、その部品の製造を終了します。
メーカーから「主要部品の供給停止」に関する通知が届いた場合、それは「今後、もしその部品が故障しても、交換する新品がありません」ということを意味します。
もし故障してしまえば、エレベーターが長期間停止するリスクを抱えることになり、居住者の生活に深刻な影響を及ぼします。
この通知が届いたら、速やかにリニューアル計画を具体化させる必要があります。
マンションのエレベーター交換費用と工期の目安
エレベーターの交換を具体的に考え始めると、次に気になるのが「一体いくらかかるのか?」そして「どのくらいの期間、不便になるのか?」という費用と工期の問題です。ここでは、その全体像を掴むための目安をお伝えします。
費用相場は800万~1500万円
エレベーターの交換(リニューアル)費用は、実施する工法やエレベーターの仕様によって大きく変動しますが、一般的な目安としては約800万円~1,500万円の範囲に収まることがほとんどです。(状況によっては、2,000万円を超えるものもあります)
なぜこれほど価格に幅があるのかというと、以下の要素が大きく影響するためです。
- エレベーターの階数・停止箇所数
- 定員(6人乗り、9人乗りなど)
- 採用するリニューアル工法(後述)
- 現在のエレベーターの状態
- 追加する機能(防犯カメラ、液晶モニターなど)
特に、後ほど詳しく解説する「どのリニューアル工法を選ぶか」によって、費用は数百万単位で変わってきます。
工期は最短3日から1ヶ月以上
工事期間も、工法によって大きく異なります。 主要な部品のみを交換する「制御リニューアル」であれば、エレベーターの完全停止期間は3日程度で済む場合もあります。
一方で、カゴやレールなども含めて全てを入れ替える「全撤去リニューアル」の場合、1ヶ月~1ヶ月半以上の期間が必要になることもあります。
工事期間中は、居住者の生活に大きな影響が及びます。特に高齢者やベビーカーを利用する世帯にとっては深刻な問題です。
費用だけでなく、この「工事期間」も、どの工法を選ぶかを決める上で非常に重要な判断材料となります。
マンションのエレベーター交換における主要3工法
「エレベーター交換」と聞くと、全てを解体して、一から新しいものを作り直す大掛かりな工事をイメージされるかもしれません。
しかし、実際にはいくつかの工法があり、マンションの状況や予算に応じて最適なものを選ぶことができます。
ここでは、代表的な3つの工法を比較し、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
| 工法 | 費用の目安 | 工期の目安 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 全撤去リニューアル | 1,500万円~ | 約1~1.5ヶ月以上 | 最新機能・デザイン導入、資産価値向上大 | 費用が最も高い、工期が最も長い |
| 部分リニューアル (準撤去リニューアル) | 900万~1,700万円 | 約3~4週間 | 費用と工期を抑えつつ一新できる | 既存部分との調整が必要な場合がある |
| 制御リニューアル | 800万~1,200万円 | 約3日~2週間 | 費用が最も安い、工期が最も短い | デザインや乗り心地は大きく変わらない |
全撤去リニューアル
既存のエレベーターを、昇降路内にあるレールなどを除き、ほぼ全て解体・撤去し、新しいエレベーターを設置する工法です。
メリットは、最新の機能やデザインを自由に選べる点です。
乗り心地や静音性も格段に向上し、マンションの資産価値向上に最も貢献します。
デメリットは、費用が最も高額になり、工事期間も最も長くなることです。
修繕積立金に余裕があり、長期的な視点で資産価値を最大化したい場合に適しています。
部分リニューアル
一般的に「準撤去リニューアル」とも呼ばれます。
制御盤や巻上機、カゴといった主要な部分は新しくしつつ、昇降路内のレールや三方枠(出入口の枠)など、再利用できる部分はそのまま活用する工法です。
メリットは、全撤去リニューアルに近い性能向上を実現しつつ、費用と工期をある程度抑えられる点にあります。
デメリットは、既存部分との兼ね合いで、デザインなどに一部制約が残る可能性があることです。
性能とコストのバランスを取りたい場合に最適な選択肢と言えるでしょう。
制御リニューアル
エレベーターの頭脳である「制御盤」や、心臓部である「巻上機」といった、性能や安全性に直結する主要な駆動・制御部分のみを最新のものに交換する工法です。
カゴや扉、レールなどは既存のものをそのまま使用します。
メリットは、何と言っても費用が最も安く、工事期間も最短で済むことです。
エレベーターの完全停止期間を最小限に抑えたい場合に非常に有効です。
デメリットは、カゴや扉のデザインは変わらないため、見た目のリニューアル感は乏しい点です。
予算を抑えつつ、まずは安全性と性能を確保したいという場合に最も合理的な選択となります。
マンションエレベーターの交換|計画から完了までの7ステップ
「よし、リニューアルの方向で検討しよう!」と決めても、実際に何から手をつければ良いのか、迷ってしまいますよね。マンションのエレベーター交換は、単なる工事ではありません。
計画の立案から、居住者の合意形成、そして実際の工事まで、長期にわたる一大プロジェクトです。 ここでは、その複雑なプロセスを7つの具体的なステップに分けて、分かりやすく解説します。
ステップ1 長期修繕計画の確認
まず最初にやるべきことは、マンションの「長期修繕計画」と「修繕積立金」の状況を確認することです。
長期修繕計画には、エレベーターの改修が何年目に予定されているか、そしてそのためにいくらの予算が計上されているかが記載されています。
この計画上の予算と、先ほどご紹介した現在の費用相場を比較し、資金が不足していないかを早い段階で把握することが非常に重要です。
ステップ2 専門業者による現状調査
次に、エレベーターの専門業者に依頼し、現在のエレベーターの状態を正確に診断してもらいましょう。
プロの目で、主要部品の劣化状況や、現在の法律に適合しているかなどを詳細に調査してもらいます。
この現状調査の結果が、どのリニューアル工法が最適かを判断し、正確な見積もりを作成するための基礎となります。
ステップ3 リニューアル仕様の検討
現状調査の結果を踏まえ、管理組合としてどのような仕様のエレベーターにリニューアルしたいかを検討します。
- どの工法を選ぶか: 予算と工期を考慮し、「全撤去」「部分」「制御」のどれを目指すか。
- 追加する機能は: バリアフリー対応(車いす操作盤、音声案内)、防犯カメラ、ペットボタン、非接触ボタンなどの要否。
- デザインはどうするか: カゴ内の壁紙や床、照明など。
全ての要望を盛り込むと費用は上がります。優先順位をつけ、どこまでを実現したいかを話し合いましょう。
ステップ4 見積もり取得と業者選定
仕様がある程度固まったら、複数の専門業者から見積もりを取得します。これを「相見積もり(あいみつもり)」と言います。
1社だけでなく、最低でも2~3社から見積もりを取ることで、費用の妥当性を判断しやすくなります。
価格だけでなく、提案された工法やアフターサービスの内容まで、しっかりと比較検討することが、業者選定で後悔しないための鍵となります。
ステップ5 管理組合での総会決議
業者と具体的なプランが固まったら、管理組合の総会に議案として提出し、組合員の承認を得る必要があります。
エレベーターの交換工事は、共用部分の重大な変更にあたるため、区分所有法で定められた「特別決議」が必要となるのが一般的です。
これは、議決権総数の4分の3以上の賛成が必要となる、非常にハードルの高い決議です。
なぜ今リニューアルが必要なのか、どの工法が最適なのか、なぜこの業者を選んだのか、といった点を、誰にでも分かりやすい資料にまとめ、丁寧に説明することが求められます。
ステップ6 工事契約と住民説明会
総会で無事に承認されたら、選定した業者と正式に工事契約を結びます。
その後、工事が始まる前に、居住者全員を対象とした説明会を開くことが非常に重要です。
工事のスケジュール、エレベーターが利用できなくなる期間、騒音や安全に関する注意点などを事前に共有することで、工事期間中のトラブルを最小限に抑えることができます。
ステップ7 着工から竣工・引き渡し
住民への周知が完了したら、いよいよ工事開始です。
工事完了後、行政の完了検査を経て、問題がなければ業者から操作方法や緊急時の対応について説明を受け、正式に新しいエレベーターが引き渡されます。
マンションのエレベーター交換で失敗しない業者選び
エレベーター交換プロジェクトの成否は、どの業者をパートナーに選ぶかにかかっていると言っても過言ではありません。
ここでは、価格、品質、そして将来の安心まで見据えた、後悔しないための業者選びの重要ポイントを3つご紹介します。
ポイント1 メーカー系と独立系の違いを理解する
エレベーターの保守・リニューアルを行う会社には、大きく分けて「メーカー系」と「独立系」の2種類があります。それぞれの特徴を理解することが、賢い業者選びの第一歩です。
- メーカー系業者
- 特徴: エレベーターを製造しているメーカー(三菱、日立など)の系列会社です。
- メリット: 製造元ならではの安心感、自社製品に関する深い知見、純正部品の安定供給。
- 注意点: 費用が高額になる傾向があります。また、提案が自社製品への「全撤去リニューアル」に偏りがちになる可能性も考慮する必要があります。
- 独立系業者
- 特徴: 特定のメーカーに属さず、独立して保守やリニューアルを行う専門会社です(私たちアイニチもこちらです)。
- メリット: 費用がリーズナブルな傾向にあります。また、メーカーの垣根を越えて、そのマンションにとって最も費用対効果の高い工法(例:制御リニューアル)を中立的な立場で提案できます。
- 注意点: 会社によって技術力や対応力に差があるため、実績などをしっかりと見極める必要があります。
ポイント2 複数社から相見積もりを取得する
前述の通り、必ず複数社から相見積もりを取得しましょう。
その際、ただ総額の安さだけで比較するのは危険です。以下の点を総合的にチェックしてください。
- 提案されている工法は適切か
- 見積もりの内訳は詳細で分かりやすいか
- 保証期間や内容は十分か
- リニューアル後のメンテナンス費用はいくらか
特に「リニューアル後のメンテナンス費用」は盲点になりがちです。
工事費が安くても、その後の保守費用が高額では意味がありません。長期的な視点でコストを比較することが重要です。
ポイント3 マンションの施工実績を確認する
オフィスビルとマンションでは、エレベーターの使われ方や求められる配慮が異なります。
マンションのリニューアルでは、居住者の生活への影響を最小限に抑えるためのノウハウが不可欠です。
その業者がマンションのエレベーターリニューアルをどれだけ手掛けてきたか、具体的な施工実績を確認しましょう。
同規模のマンションでの実績が豊富であれば、安心して任せられる可能性が高いと言えます。
マンションのエレベーター交換に関するよくある質問
最後に、管理組合の理事の皆様が、他の組合員や住民の方々からよく尋ねられるであろう質問とその回答をまとめました。総会や説明会での受け答えに、ぜひご活用ください。
Q.利用できない期間の住民への影響は
A. 工事期間中、エレベーターは完全に停止します。
階段の利用が困難な高齢者や、ベビーカー、車いすを利用する方々にとっては、非常に深刻な問題です。
業者によっては、荷物の運搬を手伝う「ポーターサービス」や、仮設の階段昇降機を用意してくれる場合もあります。
住民への配慮やサポート体制がどうなっているか、契約前に必ず確認しましょう。
Q.補助金や助成金は利用できるか
A. はい、利用できる可能性があります。
国や地方自治体によっては、エレベーターのバリアフリー改修や省エネ性能の向上などを対象とした補助金・助成金制度を設けている場合があります。
制度の内容や申請条件は自治体によって大きく異なるため、まずはお住まいの市区町村の窓口や、専門業者に相談してみることをお勧めします。
Q.リニューアル後の保証やメンテナンスは
A. リニューアルで新しく設置した部品には、通常1年~2年のメーカー保証が付いてきます。
ただし、これはあくまで部品そのものに対する保証です。エレベーター全体の安全を維持するためには、リニューアル後も継続的な保守契約が不可欠です。
リニューアルを依頼する業者に、その後のメンテナンスも合わせて任せられるか、またその際の費用はいくらかを、工事の見積もりと同時に確認しておきましょう。
まとめ
マンションのエレベーター交換は、非常に高額で、専門的な知識が求められる、管理組合にとっての一大プロジェクトです。
まずは、「交換を検討すべきサイン」を見逃さず、「費用と工期の目安」を把握することから始めましょう。
そして最も重要なのは、「交換=全撤去」と決めつけず、「全撤去」「部分」「制御」という3つのリニューアル工法の中から、ご自身のマンションの状況と予算に最も合った、賢い選択をすることです。
そのためには、特定のメーカーの都合に左右されず、中立的な立場で最適なプランを提案してくれる、信頼できるパートナー(専門業者)を見つけることが不可欠です。
私たちアイニチ株式会社は、特定のメーカーに属さない独立系のエレベーター専門会社として、これまで数多くのマンションで、それぞれの状況に合わせた最適なリニューアルプランをご提案してまいりました。
「どの工法がうちのマンションに合っているのか、専門家の意見が聞きたい」
「今の見積もりが妥当なのか、第三者の視点で見てほしい」
そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
あなたのマンションの資産価値を最大化するための、最良のパートナーとなることをお約束します。

関連記事
当社スタッフがお客様の昇降機(エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機)の状況(使用年数、故障箇所、不具合)等を伺い、必要であればリニューアル・部品交換も視野に入れた最善策をご提案いたします。
アイニチは、仙台・千葉・埼玉・東京・神奈川・名古屋・大阪・岡山・福岡の全国9箇所の拠点だけでなく、専門会社とパートナーシップを結び、全国すべての都道府県をカバーしています。(一部離島を除く)全国どこでも迅速な対応が可能です。
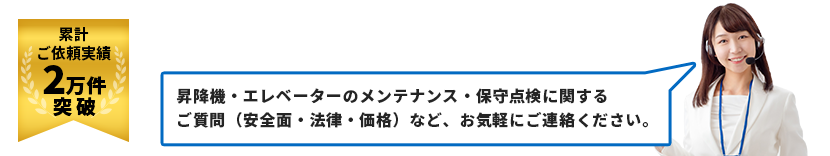

まずはお気軽にご連絡ください
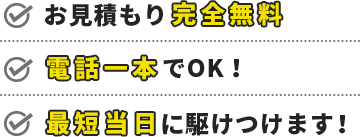
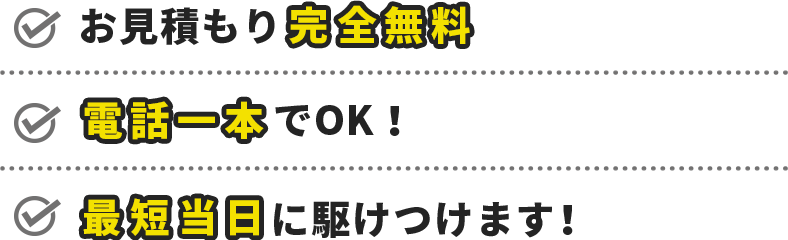
お電話でのお問い合わせ (営業時間8:30~17:30)