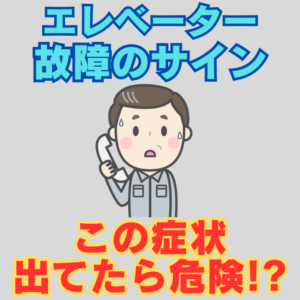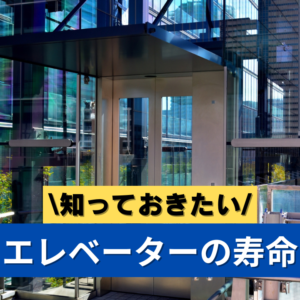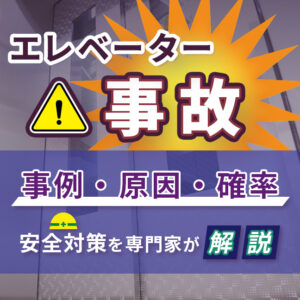豆知識
エレベーターの仕組みや構造、各部名称と役割について分かりやすく解説!
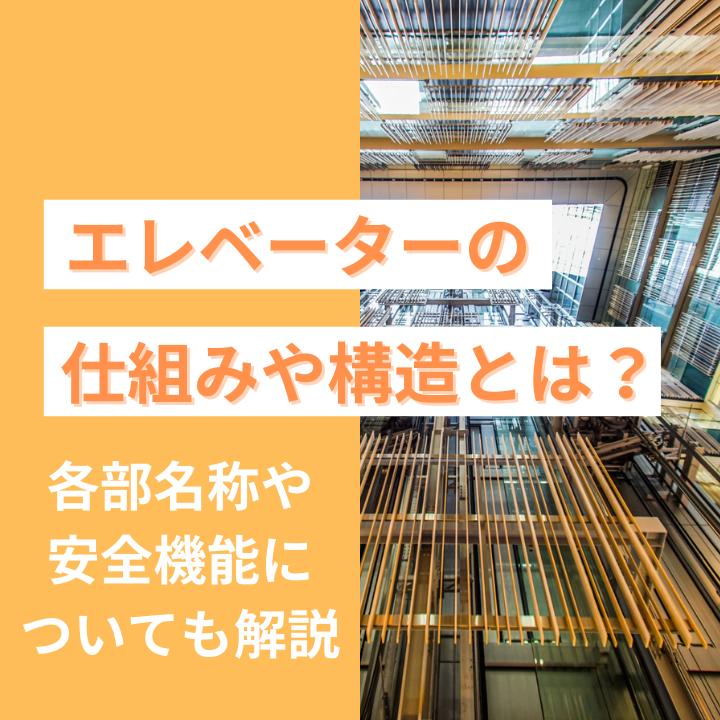
毎日のように乗っているエレベーター。ボタンを押せば静かに動き、狙った階でぴたりと止まります。
でも、なぜ安全に止まり、なぜスムーズに動けるのか、仕組みまで知っている人は多くありません。
実はエレベーターは、モーターやロープ、制御盤、ドア回りの安全装置など数多くの部品が“役割分担”して動く精密機械です。
さらに近年は、モーターの制御方法が進化し、乗り心地や電気代にまで大きく差が出るようになりました。
古い仕組みのままだと、ガタつきや待ち時間のストレス、無駄な電力コスト、部品供給停止による長期停止といったリスクが潜んでいます。
「うちのエレベーター、揺れが気になる」「電気代が高い気がする」「安全面は本当に大丈夫?」
管理者も利用者も、こうした不安を一度は感じたことがあるはず。見た目が変わらなくても、中身の“制御”や“安全装置”が古いと、快適性もランニングコストも損をします。
そこで本記事では、エレベーターが動く基本構造から、絶対に落下させない多重の安全装置、そして乗り心地と電気代を左右するモーター制御(旧式と現行の違い)までわかりやすく解説します。
あわせて、古い仕組みに潜むリスクと、その解決策となる“制御リニューアル”という費用対効果の高い改善方法も紹介。
読み終えるころには、あなたのエレベーターを安全・快適・省エネへアップデートする具体的な道筋が見えてきます。
目次
エレベーターの基本構造と動く仕組み
エレベーターはどうやって重い人や荷物を軽々と上下に運んでいるのでしょうか。
その秘密は、井戸の「つるべ」にも似た、非常にシンプルで賢い原理にあります。
ここでは、まずエレベーターの全体像と、その基本的な動作原理を解説します。
全体像を構成する主要装置
エレベーターは、主に建物の最上階に設置される「機械室」と、エレベーターが上下する通り道である「昇降路」、そして私たちが乗り降りする「乗り場」の3つの空間に分かれており、以下の装置が連携して動いています。
動力源となるモーターと巻上機
エレベーターを動かす心臓部です。
機械室に設置されており、モーターの力でロープを巻き上げたり、巻き下げたりすることで、エレベーターを昇降させます。
この巻上機の性能が、エレベーターの力強さや動きの滑らかさに直結します。
頭脳となる制御盤
エレベーターの全ての動きをコントロールする、まさに「頭脳」です。
行き先階のボタンが押されると、制御盤が巻上機に「どの階へ、どれくらいの速さで動くか」を指令します。
この制御盤の性能が、後述する乗り心地や省エネ性能に大きく影響します。
人や荷物が乗るかご
私たちが実際に乗り込む箱のことです。
この「かご」は、昇降路内に設置されたガイドレールに沿って、正確に上下運動します。
かごを支えるメインロープとつり合いのおもり
かごは、非常に頑丈な金属製のワイヤーロープ(メインロープ)で吊り下げられています。
そして、そのロープの反対側には、「つり合いのおもり(カウンターウェイト)」と呼ばれる重りが取り付けられています。
小さな力で動かすつるべ式の原理
「あれだけ重いエレベーターを、モーターの力だけで上げ下げするのは大変じゃないの?」と思うかもしれません。その通りです。そこで活躍するのが、先ほどの「つり合いのおもり」です。
エレベーターは、井戸の「つるべ」と同じ原理を利用しています。
つるべでは、片方の桶が下がると、もう片方の桶が上がります。
エレベーターもこれと同じで、かごの重さと釣り合うように「つり合いのおもり」が設置されています。
例えば、定員10名のエレベーターに5名が乗っている時とほぼ同じ重さになるよう、おもりの重量は調整されています。
これにより、モーターはかごとおもりの重量差に、乗客の重さを少し加えただけの力で動かせば良くなるのです。
この賢い仕組みのおかげで、エレベーターは最小限のエネルギーで効率的に動くことができます。
主流であるロープ式と油圧式の違い
エレベーターの駆動方式にはいくつか種類がありますが、現在の主流はここまで解説してきた「ロープ式」です。
ロープでかごを吊り上げるこの方式は、中高層の建物で一般的に採用されています。
一方、低層の建物(おおむね5階建て以下)では「油圧式」が使われることもあります。
これは、油の圧力でエレベーターを押し上げる仕組みです。
ロープ式に比べて速度は遅いですが、機械室を建物の最上階に置く必要がないなどのメリットがあります。
この記事では、より一般的で皆さんの施設にも多く採用されている「ロープ式」を中心に解説を進めます。
絶対に落下させないための多重安全装置の仕組み
「エレベーターが世界で最も安全な乗り物の一つ」と言われるのは、万が一の事態を想定した安全装置が、何重にも張り巡らされているからです。
ここでは、利用者の安全を絶対的に守るための、代表的な安全装置の仕組みについて解説します。
速度超過を検知・停止させる装置
「もしロープが切れたら…」という心配は不要です。
エレベーターには、速度の異常を検知し、強制的にかごを停止させる仕組みが備わっています。
速度を監視するガバナ
ガバナー(調速機)は、エレベーターの速度を常に監視している、いわばスピードメーター兼安全スイッチです。
もしエレベーターが決められた速度を少しでも超えると、ガバナーが作動し、次の非常止め装置に「作動せよ」という指令を出します。
強制的にレールを掴む非常止め装置
ガバナーからの指令を受けると、非常止め装置が作動します。
これは、かごの両脇に設置された強力なブレーキで、普段はかごを導いているレールを、くさび状の金属ブロックで強制的にガッチリと掴み、物理的にかごを停止させます。
主ロープが仮に全て切れたとしても、この装置が作動すれば、かごの落下を防ぐことができます。
ドアの安全を守る仕組み
エレベーターの事故で最も多いのが、ドアに関するトラブルです。
そのため、ドア周りにも様々な安全装置が設置されています。
ドアが開いたまま動くのを防ぐ戸開走行保護装置
戸開走行保護装置(こかいそうこうほごそうち)は、万が一、ドアが開いたままかごが動き出してしまった場合に、それを検知してエレベーターを緊急停止させる装置です。
2009年の建築基準法改正により、設置が義務付けられています。
ドアに挟まれるのを防ぐセーフティシュー
ドアの端に取り付けられた接触板です。
ドアが閉まる途中で人や物に触れると、それを検知してドアが反転して開きます。
最近では、接触しなくても障害物を検知できる光電式のセンサー(マルチビームドアセンサー)が主流になっています。
緊急時に作動する管制運転機能
地震や火災、停電といった予期せぬ事態が発生した際に、乗客の安全を確保するための自動運転機能も備わっています。
地震時管制運転
地震の初期微動(P波)を感知すると、エレベーターは自動的に最寄りの階に停止し、ドアを開いて乗客を避難させます。
大きな揺れ(S波)が来る前に避難を完了させるための重要な機能です。
停電時自動着床装置
停電が発生すると、多くの人は「閉じ込められるのでは?」と不安になるでしょう。
この装置は、停電を検知するとバッテリー電源に切り替わり、自動的に最寄りの階まで走行してドアを開きます。
これにより、長時間のかご内への閉じ込めを防ぎます。
乗り心地と電気代を決定づけるモーター制御の仕組み
ここまで解説してきた「基本構造」や「安全装置」に加え、エレベーターの「性能」、特に利用者が日々体感する「乗り心地」と、オーナー様が毎月支払う「電気代」を左右する非常に重要な要素が「モーター制御」です。
これは、頭脳である「制御盤」が、動力源である「モーター」をいかに賢く操るか、という技術です。
【旧式】乗り心地が悪く電気代も高い交流二次抵抗制御
1990年代頃まで主流だったのが、この制御方式です。
簡単に言うと、モーターに常に大きな電気を流し、余分なエネルギーを「抵抗器」で熱に変えて捨てることで、速度を無理やり調整していました。
車で例えるなら、アクセルを全開に踏みながら、ブレーキを踏んで速度を調整するようなものです。そのため、乗り心地がカクカクし、大量の電気を無駄に消費していました。
【現行】滑らかで省エネなインバータ制御(VVVF制御)
現在のエレベーターの常識となっているのが、インバータ制御です。
これは、モーターに流す電気の電圧と周波数を自由自在にコントロールすることで、必要な分だけ最適なエネルギーを供給する技術です。
車で例えるなら、熟練ドライバーがアクセルを非常に滑らかに、かつ繊細にコントロールするようなもの。
これにより、驚くほどスムーズな乗り心地と、大幅な省エネ性能を両立させています。
【性能比較】旧式制御とインバータ制御でこれだけ変わる
旧式と現行の制御方式では、具体的にどれくらいの差が生まれるのでしょうか。
| 比較項目 | 旧式(交流二次抵抗制御) | 現行(インバータ制御) |
|---|---|---|
| 乗り心地 | 始動・停止時に衝撃(ショック)がある | 非常に滑らかで静か |
| 停止精度 | 階との段差が数cmずれることがある | 段差がほとんどなく正確に停止 |
| 消費電力 | 大きい(余分な電気を熱で消費) | 小さい(必要な分だけ供給) |
| メンテナンス性 | 制御部品が多く複雑 | 制御部品が少なくシンプル |
あなたのエレベーターは大丈夫?古い仕組みに潜む3つのリスク
ここまで、モーター制御の仕組みと、旧式と現行方式の性能差を解説してきました。
もし、あなたのマンションやビルのエレベーターが設置から20年以上経過している場合、それは旧式の制御方式である可能性が高いと言えます。
その場合、ただ「乗り心地が少し悪い」というだけでなく、資産価値やコスト、そして安全の面で、無視できない3つの具体的なリスクを抱えているかもしれないのです。
リスク1:乗り心地の悪化による資産価値の低下
エレベーターは、マンションやビルの「顔」とも言える設備です。
そのエレベーターの乗り心地が悪いと、利用者はどう感じるでしょうか。
- 停止時の「ガクン」という衝撃
- 走行中の細かな揺れや騒音
- 階床との間にできる微妙な段差
これらは、日々の利用者にとってはストレスであり、「この建物は古い」「管理が行き届いていない」といったネガティブな印象を与えかねません。
特にマンションの場合、乗り心地の悪さは内見者の印象を大きく左右し、結果として入居率の低下や資産価値の下落に繋がる可能性があります。
リスク2:年間数十万円に及ぶ無駄な電気代の発生
旧式の「交流二次抵抗制御」が、大量の電気を熱として捨てていることは既に解説しました。
これは、例えるなら「穴の空いたバケツで水を運んでいる」ようなものです。
最新のインバータ制御方式に比べ、旧式のエレベーターは最大で50%以上も多く電力を消費するケースがあります。
仮に、毎月の電気代が2万円変わるとすれば、年間で24万円。
10年間では240万円もの大金を、本来であれば支払う必要のないコストとして失い続けていることになるのです。
リスク3:部品供給停止による長期稼働停止の危険性
これが最も深刻なリスクかもしれません。
エレベーターの部品は、工業製品である以上、メーカーでの生産には限りがあります。
設置から20年、25年と経過した古い制御方式の電子部品は、すでにメーカーが生産を終了(サプライヤーからの供給停止)していることがほとんどです。
これは何を意味するでしょうか?
万が一、制御盤の基板などの重要部品が故障した場合、交換する部品がどこにも存在しないという事態に陥るのです。
そうなれば、エレベーターは完全に停止し、復旧の目処が立たないまま長期間使用できなくなる可能性があります。
エレベーターが1台しかない建物であれば、その影響は計り知れません。
解決策は費用対効果が最も高い制御リニューアル
「リスクは分かったけど、エレベーターを丸ごと交換するのは費用が高すぎる…」
そう思われるのも当然です。しかし、ご安心ください。
これらのリスクを解決するために、必ずしもエレベーター全体を交換する必要はありません。
最も賢く、そして費用対効果に優れた解決策、それが「制御リニューアル」です。
制御リニューアルで得られる3つのメリット
制御リニューアルとは、エレベーターの「かご」や「レール」といった使える部分はそのままに、心臓部である「巻上機」と頭脳である「制御盤」など、性能を左右する主要な部分だけを最新のインバータ方式に入れ替える工事のことです。
これにより、まるで新品のエレベーターのような性能を手に入れることができます。
- 乗り心地と安全性の劇的な向上
最新のインバータ制御になることで、動き出しから停止までが驚くほどスムーズになります。階床との段差も解消され、利用者の満足度と安全性が格段に向上します。 - 大幅な省エネによる電気代の削減
消費電力が大幅に削減されるため、毎月の電気代というランニングコストを大きく圧縮できます。削減できたコストは、他の修繕費用に充てることも可能です。 - 部品供給の安定による持続的な運用
部品が最新のものになるため、将来的な故障時にも迅速な対応が可能となり、部品供給停止による長期停止のリスクから解放されます。
エレベーター全交換より費用を大幅に抑えられる理由
なぜ、制御リニューアルは全交換(全撤去リニューアル)よりも費用を抑えられるのでしょうか。
それは、エレベーターの中でも特に高価な「かご」や「三方枠(乗り場のドア枠)」、そして「レール」といった、まだ十分に使える重量物を再利用するからです。
全交換の場合は、これらの重量物を全て解体・撤去し、新たに設置するための大掛かりな工事が必要となり、工期も長くなります。
一方、制御リニューアルは主要部品の交換が中心となるため、工事費用を全交換の1/2~1/3程度に抑え、工期も短縮できるのです。
エレベーターの主要部品・安全装置用語集
ここでは、メンテナンス業者との会話や報告書で出てくる可能性のある、特に重要な専門用語をまとめました。
この記事の解説と合わせて、ぜひ参考にしてください。
駆動・昇降に関わる部品
巻上機(モーター)
エレベーターを動かすための動力源。モーターと、ロープを巻き取る滑車などで構成されています。
主ロープ(メインロープ)
かごとつり合いのおもりを繋いでいる、非常に頑丈な鋼鉄製のワイヤーロープ。複数本が束になっており、1本だけでもかごの全重量を支えられる強度があります。
つり合いおもり(カウンターウェイト)
かごの反対側に吊り下げられ、重量のバランスを取るための重り。これにより、モーターの負担を軽減しています。
安全に関わる主要装置
緩衝器(バッファー)
万が一、エレベーターが最上階や最下階を行き過ぎてしまった場合に、衝撃を和らげるための装置。昇降路の最下部に設置されています。
地震時管制運転装置
地震の初期微動(P波)を感知し、自動的に最寄りの階に停止させる装置。乗客の閉じ込めを防ぎます。
戸開走行保護装置(UCMP)
ドアが開いたまま、かごが動いてしまうといった異常を検知し、エレベーターを緊急停止させる安全装置です。
まとめ
この記事では、普段何気なく利用しているエレベーターが、いかに精緻で、安全を第一に考えられた仕組みで動いているかを解説してきました。
そして、オーナー様や管理者様にとって最も重要なことは、その仕組みを支える「モーター制御」という技術が時代と共に進化しており、古い方式のままでは、乗り心地、コスト、安全性の面で多くのデメリットを抱えてしまうという事実です。
もし、あなたがお使いのエレベーターの乗り心地に少しでも課題を感じていたり、毎月の電気代が高いと感じていたりするならば、それは古い制御方式が原因かもしれません。
最新の制御方式にリニューアルすることは、単なる修繕ではありません。
それは、居住者の満足度を高め、無駄な支出を削減し、マンションやビルの資産価値そのものを守り、向上させるための賢明な「投資」なのです。
モーター制御のような専門的な診断やご相談も、私たちアイニチ株式会社にお任せください。
現状を正確に把握し、お客様にとって最も費用対効果の高いリニューアルプランをご提案します。
関連記事
当社スタッフがお客様の昇降機(エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機)の状況(使用年数、故障箇所、不具合)等を伺い、必要であればリニューアル・部品交換も視野に入れた最善策をご提案いたします。
アイニチは、仙台・千葉・埼玉・東京・神奈川・名古屋・大阪・岡山・福岡の全国9箇所の拠点だけでなく、専門会社とパートナーシップを結び、全国すべての都道府県をカバーしています。(一部離島を除く)全国どこでも迅速な対応が可能です。
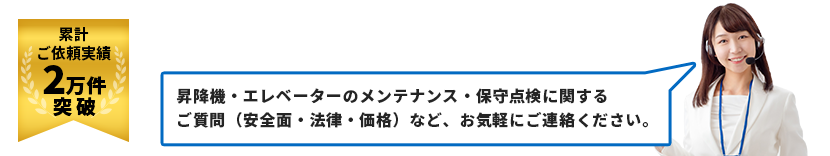

まずはお気軽にご連絡ください
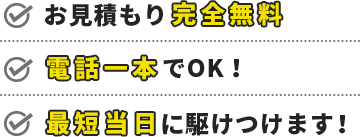
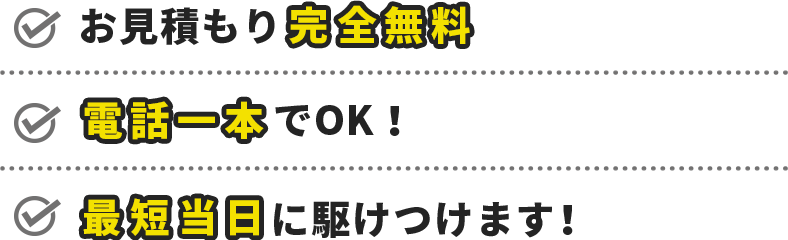
お電話でのお問い合わせ (営業時間8:30~17:30)